矯正患者の歯
不正咬合の要因
わが国の最近の50年間では、歯と顎骨の不調和による不正咬合が増加してきていることが指摘されている。歯に関していえば従来,歯の大きさは遺伝に支配されることが強く,環境の変化にはあまり変化しないとされてきた。したがって、顎だけの大きさにその原因を求める研究に注目が集まったが、そうたやすくこの問題を解決することはできない。最近では永久歯が大きくなってきていること,それが原因で歯列叢生の患者が増加してきていることなどが次々と報告されてきている。
不正咬合の成因では顎と歯の大きさの不調和が大きく関係し,その結果として歯列不正を生じている例が多いと考えられる。現在受診している矯正患者の中では歯列の叢生だけに関しては、前歯部に70%〜80%出現すると言われている。
ディスクレパンシー(歯と顎骨の不調和)の考えでは,食文化の発達に伴って食物が軟らかくなり,栄養素が濃くなったために,顎を使うことが少なくなり,これによって咀嚼器官の発達の低下が起こり, 歯と顎の大きさの不調和が起こってきたと考えられてきた(井上直彦ら)。しかし、歯の大きさに関してマウスやラットを使った動物実験からの報告でも低栄養食を与えると歯は小さくなる,妊娠中あるいは分娩後に与える食餌の種類によって仔どもの歯の大きさは変化する,高蛋白・高脂肪食の方が下顎臼歯は大きいなどと報告されている。実験動物では与える食餌が歯の大きさに影響を与えている可能性が強いと考えられる。
矯正患者と先天性欠如歯
歯並びについては社会的にも多くの人々の関心が強く,歯並びを評価の対象にしている場合さへある。歯列の異常を主訴に来院する矯正患者を調べてみると,彼らの歯列では一般の人よりも歯の先天欠如は高頻度にあらわれ,歯の大きさおよび形態においても正常咬合者との間で違いが見られる。第3大臼歯以外の歯で先天性欠如してくる歯の頻度では矯正患者が9.5%と一般集団の6.8%よりも多い。1割程度の人に欠如歯があることになる。
矯正患者の歯の大きさ
図は矯正患者と一般集団,正常咬合者にみられる歯の大きさを上下顎前歯部の歯冠近遠心径の大きさで比較した結果である(TATS値:上下顎の中切歯から第2大臼歯の歯冠近遠心径の平均値を合した値)。
歯の大きさは矯正患者集団>一般集団>正常咬合集団の順に大きさが変化しているのが分かる。大きさの変化の程度も矯正患者,一般集団,正常咬合はほとんど同じ割合でどの歯も変化している。
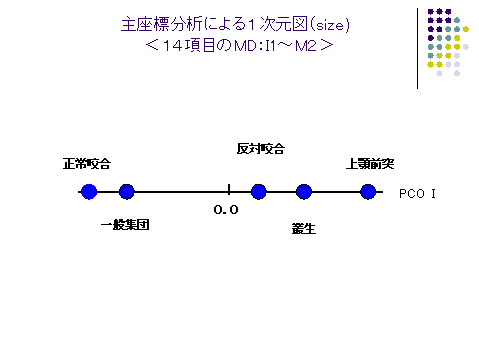
下図は女性について不正咬合者(上顎前突,反対咬合,叢生)ならびに叢生患者とその母親,一般集団のTATS値を示したものである。一般集団と比べてみると,不正咬合者は歯が大きく,なかでも上顎前突と叢生が大きいことが分かる。また叢生の娘を持つ母親も娘ほどではないが一般集団よりも歯が大きくなっている(中野誠之ら)。
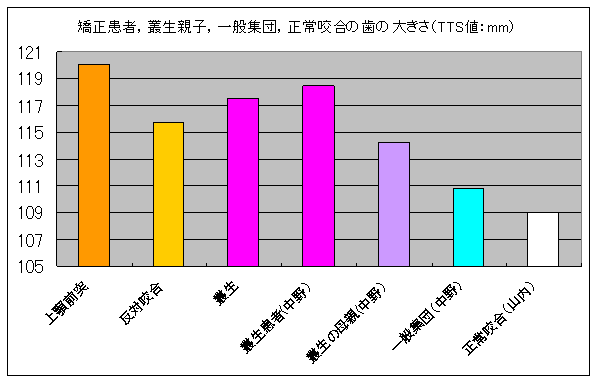
歯と顎の大きさの不調和がほとんどない集団について正常咬合者と比較した結果でも,上下顎の歯は大きい。おそらく,強い咬合力が顎骨の成長に関係するのではなく,むしろ歯の大きさの増大が叢生に強く影響していると考えられる。 進来亜希らは過去30年間における歯と顎骨の大きさの変化を調べた結果,非抜歯治療が可能な叢生患者のうち歯と顎骨の不調和がほとんどない人の歯列弓,基底弓の大きさは正常咬合者のそれと顎骨の大きさで著しい変化を見せなかったが,歯冠近遠心径の増大は強く現われたと報告している。近年みられる歯の増大の原因として,タンパク質および脂肪の摂取量が年代と共に増加していたことが考えられ,栄養摂取状態を始めとする環境因子と何らかの関連性があると思われる。
このように食環境が歯の大きさに強く影響していると述べてきたが、従来いわれてきている遺伝も極めて重要である。矯正患者の中で叢生患者の歯は大型を示すが、叢生患者の母親の歯も一般集団や正常咬合者に比べて大きい歯をしていることである。歯が大きな人からは歯が大きい子どもが生まれやすいとも考えられる。オーストラリアの歯科解剖学者タウンゼントによれば永久歯の大きさの64%は遺伝が関与しているという。遺伝と環境の両者が複雑に関係しているのであろう。